奴隷ではない
2025年7月1日、ミャンマー人の女性が日本の飲食店を相手取り、未払い賃金など計約170万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしたことがニュースになりました。ニュースによれば労働基準法が禁じている給与の天引きを行い、給料を支払わなかったとのことです。 元記事
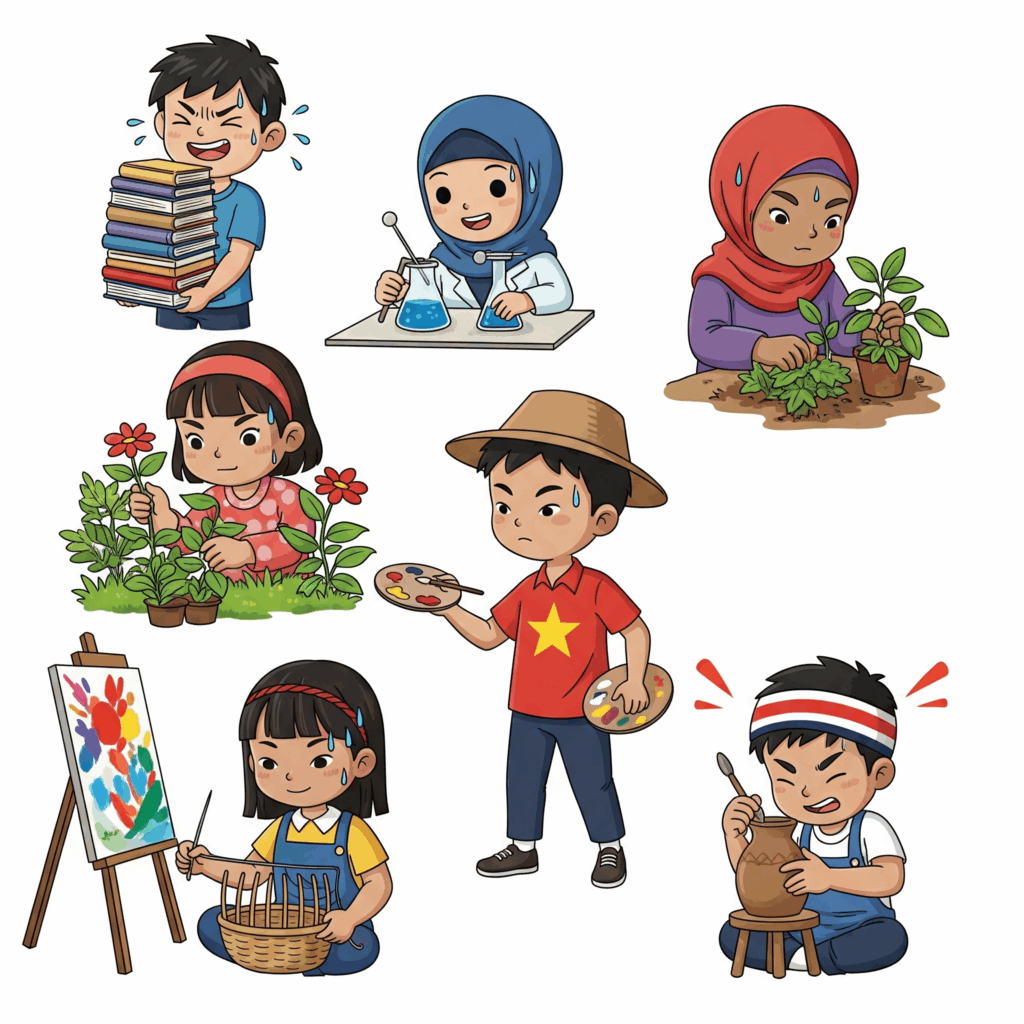
はじめに:増え続ける外国人労働者とその課題
日本社会は少子高齢化と人口減少に直面し、労働力不足が深刻化する中で、外国人労働者の受け入れが不可欠となっています。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況によると、2023年10月末時点の外国人労働者数は過去最高の約204万人に達し、前年比で約22万人(12.4%)増加しました。特に「特定技能」制度を活用した外国人労働者は、人手不足が深刻な特定産業(外食業、介護、建設など)で重要な役割を担っています。
しかし、その一方で、ミャンマー人女性がラーメン店「三ツ矢堂製麺」を相手取って訴訟を起こした事例のように、外国人労働者が不当な扱いを受けるケースも散見されます。この事例では、女性の給与から社宅の敷金・礼金や家電代などが一方的に天引きされ、初任給が「0円」となるという、労働基準法に抵触する可能性のある問題が発生しました。このような事例は、外国人労働者を「単なる労働力」と捉え、適切な対応を怠る企業側の姿勢が背景にあると考えられます。
では、外国人労働者と日本企業は、どのようにすれば健全な関係を築き、共に成長していけるのでしょうか。
日本企業が認識すべき外国人労働者とのギャップ
外国人労働者の受け入れにおいて、日本企業はいくつかの重要なギャップを認識し、埋めていく必要があります。
1. 法的・制度的理解の不足
上記の事例は、労働基準法における「賃金全額払いの原則」の軽視が根本にあります。労働者の同意なく給与から一方的に天引きすることは、原則として認められていません。特定技能制度は、外国人労働者の保護を目的とした側面も持っており、企業側にはより一層の法令遵守が求められます。
2. 文化・生活習慣の違いへの配慮不足
来日したばかりの外国人労働者にとって、日本の生活は慣れないことばかりです。住宅の手配、公共料金の支払い、銀行口座の開設など、生活の基盤を整えるだけでも大きな負担となります。企業が社宅を提供する際も、その費用負担や支払い方法について、十分な説明と合意形成が必要です。今回の事例では、これらの初期費用が一方的に給与から差し引かれたことで、女性は経済的に極めて困難な状況に置かれました。
3. コミュニケーション不足と一方的な関係性
「女性は研修内容などを理解していない」という会社側の主張は、教育やコミュニケーションが十分でなかった可能性を示唆しています。外国人労働者に対しては、業務内容だけでなく、日本の労働慣行や企業のルールについても丁寧に説明し、理解を促す必要があります。一方的な命令や不当な要求ではなく、対話を通じた信頼関係の構築が不可欠です。
外国人労働者との共生に向けた日本企業の「あるべき姿」
外国人労働者が持続的に日本社会に貢献し、企業もその恩恵を最大限に受けるためには、以下のような「あるべき姿」を目指すのが良いのではと、筆者は考えます。
1. 法令遵守と人権尊重の徹底
まず第一に、労働基準法をはじめとする関係法令を徹底的に遵守することです。給与の支払い、労働時間、休日、安全衛生など、基本的な労働条件を適切に守ることは、企業としての最低限の責務です。さらに、国籍や文化に関わらず、すべての労働者を尊重し、差別やハラスメントのない職場環境を構築することが不可欠です。
2. 包括的なサポート体制の構築
単に労働力としてではなく、共に働く仲間として外国人労働者を迎える姿勢が重要です。具体的には、以下のようなサポートが考えられます。
- 生活支援の充実: 住居の確保だけでなく、市役所での手続き、医療機関の案内、生活習慣に関する情報提供など、生活全般にわたるきめ細やかなサポートが必要です。特定技能制度では、登録支援機関による支援が義務付けられていますが、企業自身も積極的に関与すべきです。
- 日本語教育・文化理解の促進: 円滑なコミュニケーションのために、日本語学習の機会を提供したり、日本の文化や習慣を学ぶ場を設けたりすることが有効です。これにより、職場だけでなく地域社会への適応も促されます。
- キャリア形成の支援: 特定技能制度では、一定の要件を満たせば同一産業内での転職が可能です。外国人労働者のスキルアップやキャリアアップを支援することで、彼らのモチベーション向上と定着に繋がります。
3. 多様性を力に変える経営戦略
外国人労働者の受け入れは、単なる労働力補填ではありません。彼らが持つ多様な文化、知識、スキルは、企業のグローバル化や新たな事業展開の可能性を広げる大きな力となります。彼らの意見に耳を傾け、積極的に業務改善やイノベーションに取り入れることで、組織全体の活性化に繋がります。
まとめ:外国人労働者との真の共生社会を目指して
日本経済の持続的な成長には、外国人労働者の存在が不可欠です。彼らを不当に扱うことは、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、日本の国際的な評価を損ない、ひいては優秀な人材の獲得を困難にさせます。
2023年4月に外国人材の受け入れ・共生に関する政府の有識者会議が取りまとめた報告書では、「共生社会の実現」に向けた提言がなされています。これには、生活支援の強化、日本語教育の充実、多文化共生の地域づくりなどが盛り込まれており、政府、企業、そして社会全体が一体となって取り組むべき課題として認識されています。
外国人労働者と日本企業が真に共生し、共に成長していくためには、企業側が法令を遵守し、人権を尊重し、そして多様性を積極的に受け入れる姿勢を持つことが何よりも重要です。これにより、外国人労働者は安心して能力を発揮でき、企業は持続的な発展を遂げることができます。今回の事例を教訓として、より良い未来を築いていくための努力が、今、日本社会全体に求められているでしょう。人間同士の話で、しかも多文化も混ざると難しいですが、頑張っていきましょう。



